
|
して取り上げられてもいるわけです。アメリカの鯨捕りの連中は、陸の人間とは区別された存在として扱われていたところがあるようですが、逆にメルヴィルは鯨との戦いを繰り広げる鯨捕り漁師も非常に崇高な存在だと力説しているわけです。日本の場合も、刃刺などは尊敬される存在として扱われているところがあります。殺生が差別につながる場合もあるのにこれは興味深いことだと思います。
谷川…シャチから追われて、湾の中に入り砂浜に乗り上げた鯨は、海の幸・寄鯨(ヨリクジラ)として海神の贈り物のような自然の受け取り方があった。それから、だんだん沖合へ出てきて、人為的に追い込んで、網をかけてということになると、やはり感情的には、海の幸として海神に感謝するところが仮にあったとしても、少し違ってくるのではないでしょうか。折口信夫が壱岐の『採訪記』の中で、リョウエビスを書いている。これは解体した鯨から胎児が出てきた。それは非常に手厚く葬ったとある。それをリョウエビスと言っている。エビスだから海の幸と呼んだかもしれないけれど、胎児を厚く葬るというところに、鯨に対する感情が普通の動物とは違う何かが動いているかもしれないと私は思うんです。
中園…そうですね。初めは流れ着いたあるいは寄ってきた鯨もイルカも村が潤う、エビス的な存在として扱われていたと思います。ところが江戸時代の段階でイルカ漁は、昔通りの漁業形態でいったのですが、鯨漁はだんだんと企業経営的な側面が西海では特に強くなっていった。カンダラされる肉が経営的にはロスだと考えられていくような意識が一方ではあった。ところが鯨組の中でも、鯨の供養だとか、鯨をたくさん捕るために、鯨の肉を土地の氏神様に供えるとか、そういう昔ながらの信仰的なものも引きずっているところもある。しかしそのような伝統的な意識も段々と企業の利潤追求一辺倒のカラーに染まってしまい、最終的には戦後の南氷洋における補鯨オリンピックのような状態になってしまったと思うのです。
谷川…企業のためにいくら捕ってもいいという日本人の持つえげつなさを見るわけです。鯨が泳いでいれば捕ってもおかしくないではないか、という日本の企業第一主義、そういうあられもない精神を日本人は見せつけるから、海外から鯨捕りに対する糾弾も強くなるのではないですか。
中園…神の領域、それとも精神的な領域でしょうか、それが産業的な部分が強くなるにつれて減ってしまい、同時に鯨を一つの生き物として扱う意識も希薄になっていった。それが鯨文化の衰退という現象につながっているのかも知れませんね。
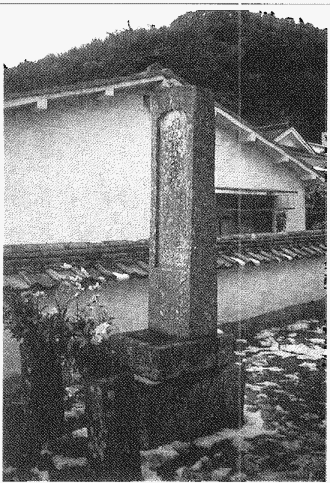
鯨墓[山口県長門市通浦、元禄五年(一六九二)建立 島の館提供]
◎生月の冬と春の鯨◎
谷川…鯨が、生月島の近くを通って冬に南に向かい、春に北に向かう姿は非常に壮観ではなかったかと思います。潮を吹きながらゆうゆうと海の王者が通っていく姿は、一種の美しさというか、神として畏敬の念を払わざるを得ないと、私は空想的に考えているのですが、実際、冬と春の鯨は、どういうふうに通って行ったのでしょうか。
中園…秋も深くなって、どちらかというと冬になるくらいの頃ですが、その頃に境は夏の間にオホーツク海で餌を取っていた鯨たちが、子どもを産むということもあり、だんだんと南下していくわけです。秋頃から動き始めるのですが、南下する集団のうち日本海のほうを行く鯨が、冬の初め頃から朝鮮海峡、
前ページ 目次へ 次ページ
|

|